雰囲気で叩く誘導報道をここで終わらせるべき
とにかく自民党批判の多くは、なんだかよく分からないけどイヤだから批判しようっていうモノが多いような気がしてなりません。
例えば野党なんかは「安倍独裁政治をとめよう」なんて言ってますが、自分たちだって民主主義制度の中で選ばれた国会議員であるにも関わらず、同じ選挙で当選して総理になっている安倍さんに対して独裁政治っていう言葉を使うコト自体がナンセンス甚だしいワケです。
そもそももし本当に独裁という状態になっているのであれば、それはむしろ総理や政治家などの人間の行動が問題なのではなく、独裁を許す制度の問題であるハズなんですね。
独裁と言えばすぐに名前が挙がるヒトラーですが、ヒトラーだってなんとなく独裁体制になっていたのではなく、キチンと憲法や法改正などを行って(しかも国民の支持を得ながら)独裁体制を整えたワケで、もし戦後ずっと変わらない憲法を持ち続けている今の日本において独裁という状態が安倍さんの登場だけで成し得ているのであれば、それは共産党も含めた全ての国会議員が法や制度の不備を見つけられなかっただけとしか言いようがなく、そういう批判は大変に無責任なモノでしかないと言うしかありません。
こういう視点からも、安倍内閣に対して独裁という言葉を使うのは不適切極まりない行為でしかなく、結局いま野党が行っている批判というモノは、独裁という言葉が持つ本質的な意味で批判しているのではなく、ただ単にその響き・雰囲気で相手にレッテル付けをして叩いているだけの、本当にくだらないネガティブキャンペーンでしかないと断じざるを得ないのです。
マスコミなんかはもっとヒドイです。
最近よく聞きませんか?
「自民党はイヤだけど、野党も頼りない。だから選挙に関心がない」
しかし自民党がイヤっていう言葉は、果たして具体的に何を指し示している言葉なのでしょうか。
野党が頼りないっていうのはまだ具体性があります。
民主党は与党の時の政策的失敗はそれを挙げようと思えばキリがないほど挙げるコトができますし、野党に転落してからも、また昔の55年体制の時の野党かのように与党の足を引っ張るコトしかできなかったコトを考えれば、民主党に対しては頼りないという言葉すら不適切ではないかと言うしかありません。
また維新の党も、結局分裂と合流、党内権力争いに明け暮れ、党首であるハズの橋下大阪市長も何をしたいのかよく分からない、いえ誰かとケンカしたいのだけは分かりますが、しかしその得意(?)のケンカも今回の選挙の出る出る詐欺で終わってしまっている有様を見れば、「頼りない」と言うよりも「情けない」と言ってしまう方が適切なのではないかと言うしかありません。
野党各党のこの2年間、プラスの方向で特筆すべき点があるのであれば、ぜひとも教えてもらいたいと本当に願うぐらいです。
しかし自民党に対する「イヤ」ってなんなのでしょうか。
当たり前ですが、自民党に対して批判するななんて言うつもりは毛頭ありません。
だけどただ単に「イヤ」って中身も無く言ってしまうのであれば、仮にも公党に対しての言葉としては、それはあまりにも不適切でしょう。
いつも言っていますが、批判するなら具体的に指摘するべきです。
ですから、集団的自衛権がイヤだとか、円安株高がイヤだとか、そういう政治的信念を持って自民党を批判し、となれば社民党や共産党を支持するっていうのでしたら、それはその人の考え方ですから、その考え方の存在までをも否定するつもりはありません。
そういう人も、日本の中に一定数はいるでしょう。
それならそれでいいんです。
でも少なくとも、「なんとなくイヤだ」と、それをマスコミが堂々と口にしてしまう、文章にしてしまうっていうのは、あまりにネガティブキャンペーンにも程があると思いますし、そもそもそんな薄っぺらく無責任なコトを公の場で言ってしまうのは本来恥ずかしいコトだと多くの人が認識すべき行為なのではないのでしょうか。
「解散の大義がない」とかいうのもそうです。
民主主義国家において意味のない選挙なんてありはしないでしょう。
むしろ「選挙に意味がない」と言うのは「現政権に100%全賛同する」と言っているようなモノでしょう。
現政権に1ミリも不満が無いのであれば、それは確かに選挙をする意味はないのかもしれません。
でも現実は、安倍政権に批判的な人ほど「選挙に大義がない」とか言っているのです。
それなのにこの自己矛盾に気付いている人はほぼいないんですね。
結局これも、中身無きネガティブキャンペーンというコトなのです。
そろそろこういう雰囲気で政治を語るような無様なマネはやめるべきでしょう。
なにより、マスコミのミスリードに対しては国民の方からNoを突き付けるべきです。
もう日本人は雰囲気だけで決定される選挙の恐ろしさを身をもって体感しているハズなんですからね。

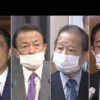


ディスカッション
コメント一覧
本日の朝日社説のことですね。
クリスマスを控え、街のあちこちはイルミネーションに彩られている。幻想的な光の渦の中で、家族連れは記念写真を撮り、恋人たちは手をつなぎ、満ち足りた表情を浮かべている。
東日本大震災が起きた2011年、夜は一段暗かった。被災地から遠く離れた街でも、街頭を明るく照らす自動販売機を見ればなんとなく申し訳ない気持ちになり、エアコンを入れる時は、彼の地で暮らす知らない誰かに思いをはせた。
「絆」とか「日本人として」とか大上段に構えなくても、同じ国に暮らす者としての共感、「私たち」という感覚があったように思う。
さらにさかのぼれば、民主党への政権交代後しばらくは、沖縄の米軍基地の問題も、「私たち」の問題だった。誰かに負担を押しつけて知らん顔をする、それでいいのだろうか、と。
「私たち」は真剣に考えたのではなかったか。この国はこれからどのような道を歩むべきなのか。本当の豊かさとは何だろうか。だが、そんなことがあったという社会的な記憶すら、もはやあいまいだ。「私たち」はほどけて「私」になり、ある部分は政治的無関心へ、ある部分は固くて狭い「日本人」という感覚にひかれてゆき、気がつけば、この社会にはさまざまな分断線が引かれるようになった。
■分かち合いは可能か
「死ね」「殺せ」「たたき出せ」。街頭にあふれ出す、特定の人種や民族への憎悪をあおるヘイトスピーチ。雑誌やネット上に躍る「売国奴」「国賊」の言葉。選挙戦では、特定の候補者の名誉にかかわる悪質なデマが、ネット上で拡散された。
線の「あっち側」を攻撃したり排除したりすることで得られるのは刹那(せつな)的な連帯感。それを政治的資源にしようとする政治の動きも目立ってきた。
今回の選挙では、個々の政策への賛否とは別に、「私たち」をどう再び築いていくかという問いが、政治家だけでなく、有権者ひとりひとりにも投げかけられている。利益を配分すればよかった時代から、負担を配分しなければならない時代に入ったと言われて久しい。
しかし、被災地の復興にせよ、社会保障にせよ、「私たち」の感覚が失われた社会では、誰かに負担を押しつけることはできても、分かち合うことはできない。
■決める道具ではなく
とはいえ、そんなことを言われるほどに気鬱(きうつ)になり、棄権に傾く人もいるだろう。いったい何を選べというのか。そもそも自分が一票を投じたところで、いったい何が変わるのか。
確かに一票は、限りなく軽い。ただ、「私」の一票が手元を離れ、「私たち」の民意になることには意味があり、それは選挙の勝敗とは違う次元で重んじられなければならない。一票が群れて民意を成す。そこに政治を変える可能性が生まれる。
民意は数の多寡だけではかられるべきものではない。1990年代の政治改革以来、多様な民意を反映させることよりも、「決める」ことこそが政治だという政治観が広がった。
政治家も、有権者も、民意というものへの感受性を鈍らせ、勝ち負けを決めるための、ただの「道具」のようにとらえる向きがあるのは、おかしい。「私たち」は道具ではなく、この国の主権者である。自信と誇りをもって、自らに代わって議する者に、意思を示し続けなければならない。
信頼できる人に入れる。好きな政党に入れる。勝敗にコミットしたければ、小選挙区ではより勝たせたい方に入れる。やり方は自由だ。一票を投じる。政治が本来持っているはずの豊かさと潤いを取り戻すための一歩として。
どうやら彼らにとっては自民党の票=ろくでなし、民主党の票=正義、だとか。正に二枚舌であり、誤報(捏造)もなんのそののようです。